
QCとは何か
QCとはクオリティコントロール(品質管理)である。果たして本当にコントロールが行われているだろうか。筆者の経験では、多くの企業ではチェックばかり繰り返されている。であればクオリティチェックと言えばよいのではないか。なぜクオリティコントロールというのだろうか。これが最初の疑問である。
コントロールとは一体何だろうか。コントロールとは、標準からずれそうになったり、ずれたりしたプロセスを標準に戻す活動のことである。
わかりやすく言えば野球の例がある。野球でピッチャーがストライクゾーンを狙って投球をする。これをコントロールという。QCとは、品質のストライクゾーンを目指してプロセスをコントロールすることである。
その品質のストライクゾーンとは一体どこに記載されているだろうか。その品質のコントロール、つまり品質のストライクゾーンは、SOP(標準業務手順書)に記載されている。
ここで注意すべきことがある。日本語では「管理」という言葉を使うが、英語では2通りに分かれる。一つはコントロール、もう一つはマネジメントである。
この違いは、マネジメントは野球でいうところの監督に相当し、コントロールはピッチャーに相当する。マネジメントは各部門の部課長クラスの管理職が現状を見て指示を出すことである。一方で、現場の者が自身の作業をしながら、SOPに従ってコントロールし、ストライクゾーンを狙うのがQC(コントロール)に相当する。つまり、全員がピッチャーの立場にいるのである。
品質の標準(ストライクゾーン)は、標準業務手順書(SOP:Standard Operating Procedure)または、GMPの製造所などの場合は製品標準書に記載されている。そのストライクゾーンを狙って業務をコントロールすることが、クオリティコントロールである。
例を挙げて説明する。ある外注業者に1,000個のデータ入力を依頼したとする。契約において、0.3%のエラーまでなら受領すると約束した。データ入力を終えたデータを受け取り、チェックを始めると、1個、2個、3個、4個とエラーが見つかった。
これで契約で取り決めた0.3%のエラーを超えてしまった場合、「0.3%のエラーを超えましたのでこの納品は受け取れません」と言って、当該業者に差し戻す。
このとき重要なことがある。どこにエラーがあったか教えてはならない。なぜなら、もしエラーの箇所を教えてしまうと、その業者は指摘されたエラーの箇所だけを修正して再度提出するからである。そうすると、追加の残りのチェックをまた行う必要が生じる。
また、何個エラーがあったかも教えてはならない。個数を伝えると、その数だけエラーを修正したら再提出されるだろう。そうなると、また残りのエラーチェックをする必要が生じる。
これは決して良い状態ではない。後段のプロセスで、後のプロセスの人が当事者に成り代わってデータをチェックし、さらに修正までするというやり方では、いつまでたってもデータの品質が向上しないというジレンマに陥る。
これは極めて重要なことである。QCで必要なことはチェックをするだけではなく、きちんと差し戻すことが重要である。いい加減な作業や品質の悪い作業をすると差し戻されるという事実が、一つの抑止力になる。その結果、当事者はデータの品質管理・品質保証により注力するようになる。
ここで誤解しないでほしいのは、チェックはQCではないと言っているわけではないことである。ただ、チェックだけではQCにならないということである。きちんとコントロールをしなければならない。
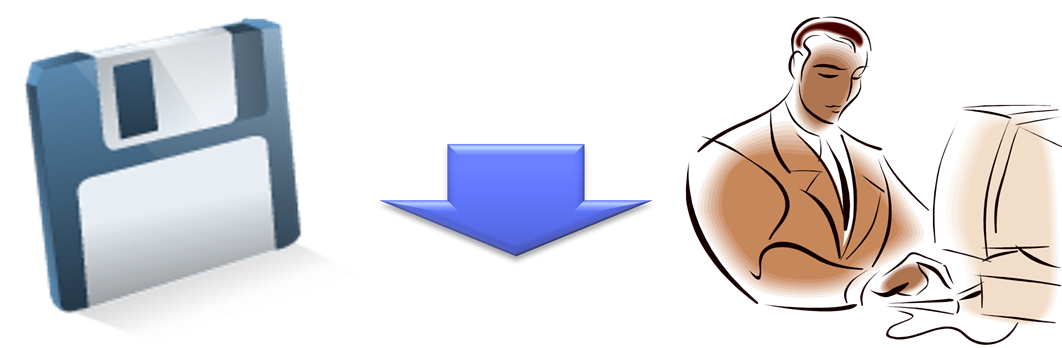
前述の例のように、標準からずれたものに対しては、プロセスに戻して標準に合うようになるまで次のプロセスに進めないことが、クオリティコントロールである。これは極めて重要なプロセスである。
別の例も挙げよう。あるクッキー工場で製造指図書に、クッキーは170℃±5℃で焼くと記載されているとする。バーナーの担当者は、175度を超えそうになると火力を下げ、165度を下回りそうになると火力を上げる。
なぜなら、175度を超えると焦げてしまい、165度を下回ると半生になってしまうからである。つまり、170度±5度という指図書に記載された温度範囲で焼くことで、あらかじめ定めた美味しいクッキーが焼き上がるのである。
これがクオリティコントロールである。つまり、SOPに従って業務を行えば、必ずあらかじめ定めた仕様で、あらかじめ定めた品質で製品が製造できるはずである。それでも正しく製品の品質が仕様を満たさなかったり、サービスが提供できなかったりする場合は、SOPが間違っている、標準が間違っているということになる。
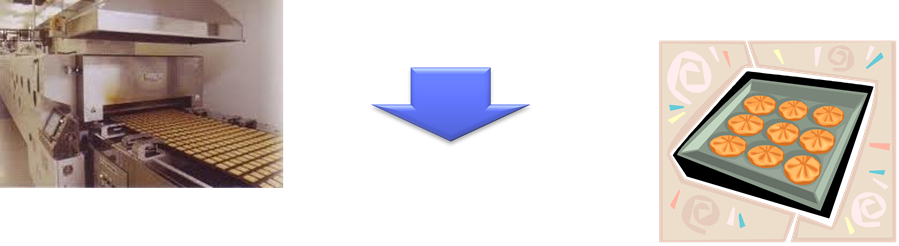
関連商品







