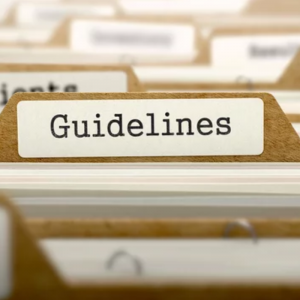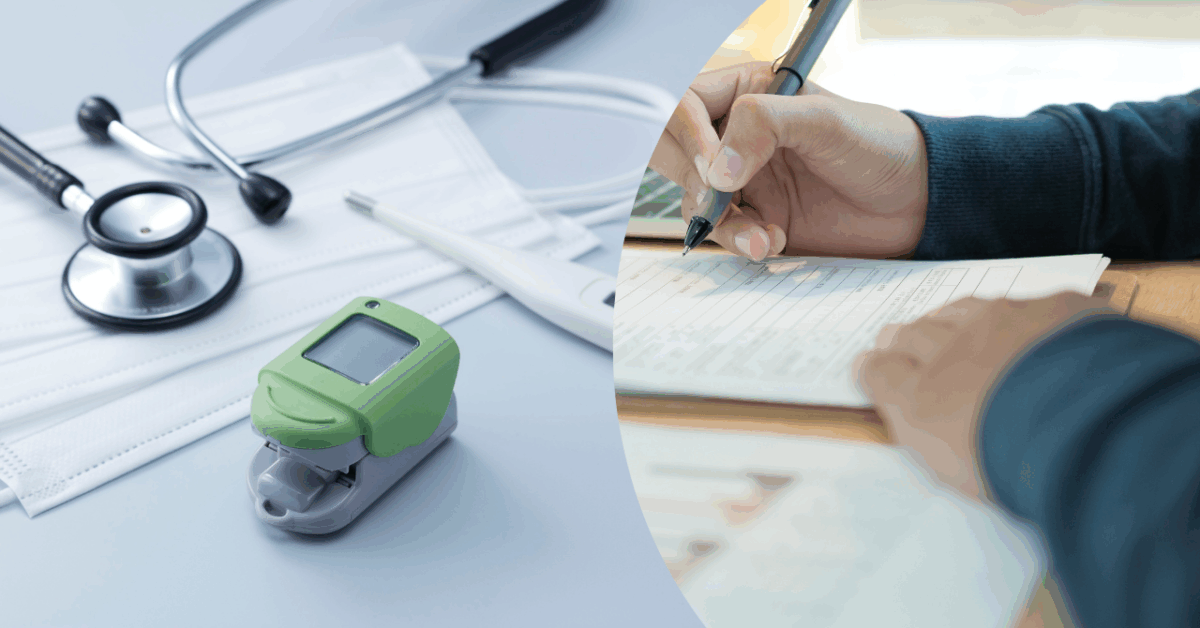
日米における医療機器薬事規制での変更申請の相違について
はじめに
医療機器は人命に関わる製品であるため、その開発から販売、市販後に至るまで厳格な規制が課せられている。特に製品の変更時には、変更内容に応じた適切な申請が必要となる。本稿では、日本と米国における医療機器の変更申請制度の相違点について解説する。医療機器メーカーが国際展開する際に必要となる基本的な知識を整理することを目的としている。
日本における医療機器変更申請制度
1. 法的枠組み
日本では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)に基づき、医療機器の変更管理が行われている。承認を受けた医療機器の変更は、その内容により以下の3つに分類される。
- 一部変更承認申請(承認事項一部変更承認申請、PAPR)
- 軽微変更届出(軽微変更届、MCN)
- 変更計画確認申請制度(PACMP)
2. 一部変更承認申請(PAPR)
製品の品質、有効性、安全性に影響を与える重要な変更の場合、一部変更承認申請が必要となる。具体的には以下のような変更が該当する。
- 使用目的・効能効果の変更
- 形状・構造・原理の重要な変更
- 原材料の変更(生物由来材料等)
- 性能・安全性に関わる設計変更
- 滅菌方法の変更
新規医療機器の承認審査期間が9〜18ヶ月程度であることから、変更申請においても相応の審査期間を要する場合がある。この間は原則として変更を実施することができないため、製品開発サイクルに大きな影響を与える場合がある。
3. 軽微変更届出(MCN)
品質、有効性、安全性に影響を与えない軽微な変更の場合、軽微変更届出で対応できる。届出は変更実施後30日以内に行えばよく、PMDAの事前承認は不要である。以下のような変更が該当する。
- 製造所の名称変更、所在地の変更(製造工程に影響しない場合)
- 製造方法の軽微な変更(重要工程に影響しないもの)
- 規格及び試験方法の軽微な変更
- 表示の変更(警告・禁忌以外)
- QMS適合性調査が不要な変更
4. 変更計画確認申請制度(PACMP:Post-Approval Change Management Protocol)
2020年(令和2年)の薬機法改正により導入された新しい制度である。変更内容とその評価方法をあらかじめPMDAに申請し確認を受けておくことで、変更実施後は結果の届出のみで良くなるという制度である。変更計画に従った変更であれば、一部変更承認申請が必要な変更であっても、届出のみで対応可能となる。
米国における医療機器変更申請制度
1. 法的枠組み
米国では「連邦食品・医薬品・化粧品法」(FD&C Act)に基づき、FDAが医療機器を規制している。変更管理については主に以下の申請形態がある。
- PMA Supplement(市販前承認補足申請)
- Special 510(k)(特別510(k))
- 30-Day Notice(30日前通知)
- Annual Report(年次報告)
- Letter to File(社内文書)
2. PMA Supplement(市販前承認補足申請)
PMA(Premarket Approval)承認を受けた医療機器(クラスIII機器)の重要な変更に対する申請である。変更の内容により以下のように分類される。
- Panel Track Supplement:新たな適応症の追加など最も重要度の高い変更
- 180-Day Supplement:重要な設計変更、重要な製造工程の変更など
- Real-Time Supplement:比較的軽微だが審査が必要な変更(90日程度で審査)
- 30-Day Notice:製造工程の変更(特に品質システムに関わる変更)
3. 510(k)関連の変更
510(k)クリアランスを受けた医療機器(主にクラスII機器)の変更は、以下のように対応する。
- 新規510(k):安全性・有効性に大きな影響を与える変更
- Special 510(k):設計管理の下で行われる変更で、当初の使用目的に変更がない場合
- Letter to File:安全性・有効性に影響を与えない軽微な変更
4. Letter to File(社内文書)
日本の軽微変更届出に相当するが、一定の条件下ではFDAへの届出は不要で社内文書として保管するケースがある。製品の安全性・有効性に影響を与えない以下のような変更が該当する。場合によっては性能データのサマリー提出が必要となることもある。
- ラベリングの編集上の変更
- 部品供給業者の変更(同等性が証明できる場合)
- 製造工程の軽微な変更
- 品質管理試験方法の改善
日米の変更申請制度の主な相違点
1. 承認前の変更実施可否
日本では一部変更承認申請の場合、原則として承認を得るまで変更を実施することができない。米国でも基本的にはPMA Supplementの場合、変更実施前に申請が必要であるが、30-Day Notice制度では、FDAが30日以内に異議を唱えない限り変更可能となる特例がある。
2. 判断の自由度
米国のLetter to Fileのように、企業の判断で変更を実施し文書化するのみでよい制度が米国には存在する。日本では基本的に軽微な変更でも届出が必要であり、企業の裁量範囲が米国に比べて狭い傾向にある。
3. 審査期間と透明性
日本の一部変更承認申請は新規申請と同様に長期間を要することがあるが、明示的な審査期間の目標は公表されていない。一方、米国では変更の種類によって30日、90日、180日など、より細分化された審査期間の枠組みが設定されており、例えば510(k)では90日目標が公式に提示されているなど、審査期間の透明性が高い。
4. 変更計画の事前確認
日本のPACMPと米国のReal-Time Supplementは類似した概念であるが、日本のPACMPは比較的新しい制度であり、まだ活用事例が少ない。米国ではより長期間にわたり変更管理の効率化が進められてきた。
企業の国際戦略における留意点
1. 開発計画への影響
日米で変更申請の要件や審査期間が異なるため、グローバル開発を行う企業は、最も厳しい規制に合わせた開発スケジュールを組む必要がある。特に日本で一部変更承認申請が必要な変更を行う場合、米国よりも長い審査期間を見込んでおくべきである。
2. 変更管理システムの構築
国際展開する企業は、各国の規制に対応できる変更管理システムを構築することが重要である。特に同一変更に対して国によって必要な資料や手続きが異なる点に注意が必要である。
3. 新制度の活用
日本のPACMPや米国の各種迅速審査制度など、規制当局も変更管理の効率化に取り組んでいる。これらの新制度を積極的に活用することで、開発サイクルの短縮が可能となる場合がある。
4. 国際調和への対応
近年、日米間では規制調和の取り組みが進展しているが、依然として日本は独自の規制要件を維持している部分がある。一方、米国はGHTF(Global Harmonization Task Force)などの国際基準をより重視する傾向にある。企業はこれらの動向を把握し、各国の規制変更に迅速に対応できる体制を整えることが重要である。
おわりに
日米の医療機器変更申請制度は、同じ目的を持ちながらも異なるアプローチで運用されている。企業はこれらの違いを理解した上で、効率的かつコンプライアンスを遵守した変更管理を行うことが求められる。今後も各国の規制調和が進むことが期待されるが、当面は各国の制度の違いに対応した戦略立案が必要である。
医療機器のグローバル展開を目指す企業にとって、変更管理は避けて通れない重要な業務である。本稿が医療機器の変更申請に関わる実務担当者の一助となれば幸いである。
関連商品