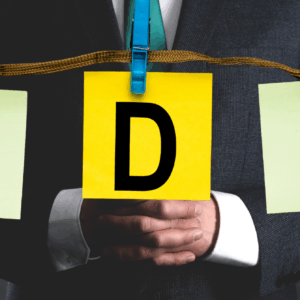重大性はリスクコントロール後も変化しない
リスクコントロール後も変化しない重大性
はじめに
リスクマネジメントの世界では、多くの誤解や混乱が存在する。特に「リスクの重大性はコントロール措置によって変化するか」という問いについては、初心者から専門家まで様々な見解が交錯している。今回は、この問題に焦点を当て、リスクの重大性がコントロール後も本質的に変化しない理由を解説する。
リスクの基本要素を理解する
まず、リスクの基本的な構成要素を確認しておこう。リスクは一般的に次の二つの要素から構成される。
- 発生可能性(確率):事象が発生する確率
- 重大性(影響度):事象が発生した場合の影響の大きさ
これらを数式で表すと
リスク = 発生可能性 × 重大性
となる。この理解が、以下の議論の基盤となる。
重大性の本質
重大性とは、「ある事象が発生した場合に生じる結果の深刻さ」を表す。これは以下のような要素を含む。
- 人的被害(死亡、怪我など)
- 金銭的損失
- 環境への影響
- 社会的評判の毀損
- 法的責任
重要なのは、重大性は「事象が発生した場合の」影響を測るものであり、発生前の予防措置には直接関係しないという点である。
リスクコントロールの本質
リスクコントロールには主に二種類ある。
- 予防的コントロール:発生可能性を下げるための措置
- 影響緩和コントロール:事象が発生した場合の影響を軽減するための措置
ここで注意すべきは、予防的コントロールは発生可能性のみに作用し、重大性には影響しないという点である。
なぜ重大性はコントロール後も変化しないのか
重大性がコントロール後も変化しない理由は、以下のように説明できる。
1. 理論的根拠
リスクの定義に立ち返ると、重大性は「事象が発生した」という条件付きの概念である。予防的コントロールは発生前の措置であるため、事象が発生した場合の結果(重大性)には影響しない。
例えば、高所から落下するリスクを考えよう。安全帯の着用(予防的コントロール)は落下する確率を下げるが、もし実際に落下した場合の重大性(地面に衝突する衝撃)は変わらない。
2. 実務的な誤解
実務の現場では、予防的コントロールと影響緩和コントロールが混同されることがある。例えば
- 誤った理解
:「安全対策を施したので、このリスクの重大性は下がった」 - 正確な理解
:「安全対策により発生可能性は下がったが、もし発生した場合の重大性は変わらない」
3. 影響緩和コントロールと重大性の関係
影響緩和コントロールは、一見すると重大性を変えるように思えるが、実は新たなリスクシナリオを作り出しているに過ぎない。
例えば、化学プラントで防火壁を設置する場合
- 元のリスクシナリオ:「火災が発生し、全施設に広がる」(高い重大性)
- 新たなリスクシナリオ:「火災が発生し、防火壁で区画された範囲に留まる」(相対的に低い重大性)
これは重大性が変化したのではなく、異なるリスクシナリオを定義し直したことになる。
実践的な応用
この理解は、リスクアセスメントにおいて極めて重要である。
- リスク評価の明確化:リスクの発生可能性と重大性を別々に評価し、コントロール措置がどちらに作用するかを明確にする。
- 効果的なリスクコミュニケーション:「このコントロール措置によってリスクの重大性は変わらないが、発生可能性が下がる」という正確な説明ができる。
- リスク対策の優先順位付け:高い重大性を持つリスクには、発生可能性を極限まで下げる対策が必要となる。
結論
リスクコントロール後も重大性が変化しないという理解は、効果的なリスクマネジメントの基盤である。この概念を正しく把握することで、より精緻なリスク評価と対策が可能となる。重大性と発生可能性を明確に区別し、それぞれに適したコントロール措置を講じることが、リスクマネジメントの本質である。
特に注意すべきは、重大性が高いリスクに対しては、発生可能性をゼロに近づける努力が不可欠であり、「重大性は下がらないが、発生可能性を極限まで下げる」という正しい考え方に基づいた対策が求められるということである。
関連商品