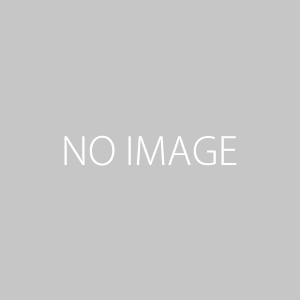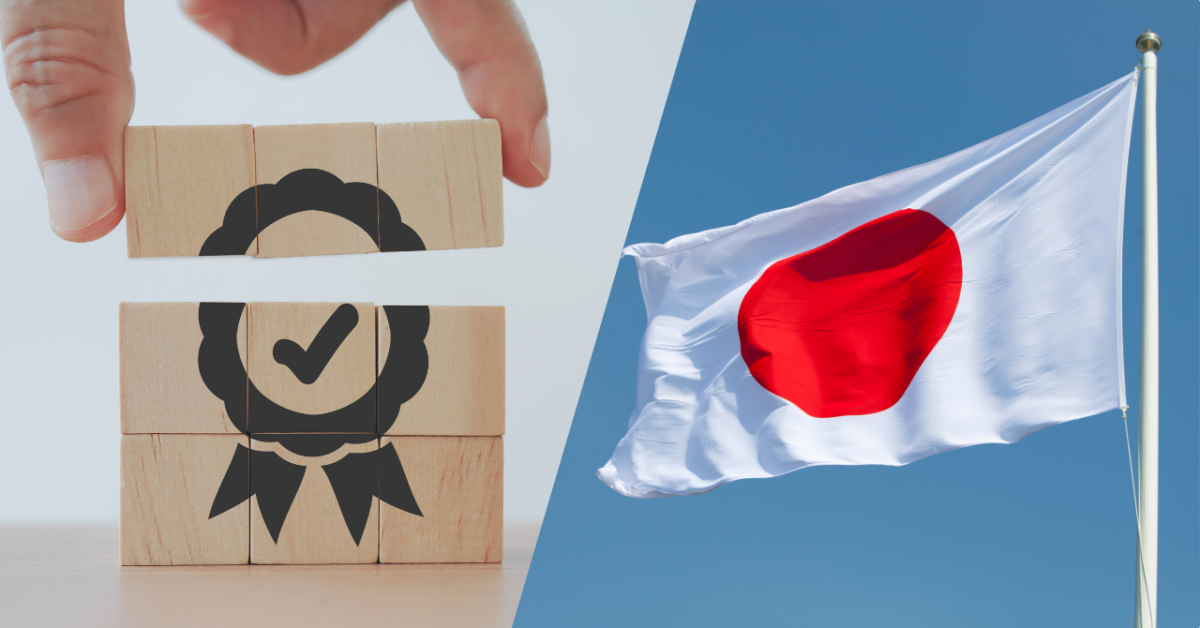
JIS規格番号の体系と採番ルール
日本産業規格(JIS)の規格番号は、体系的な構造を持ち、規格の分野や内容を効率的に識別できるように設計されている。
基本構造
JIS規格番号は、次の三つの主要な要素によって構成される。
- 第一の要素は部門を表すアルファベット1文字であり、規格が属する技術分野を示している。
- 第二の要素は4桁から5桁の数字で、規格の分類と通し番号を表している。
- 第三の要素は発行年を示す4桁の数字であり、コロンの後に記載される。
例えば「JIS Z 8301:2008」という規格番号の場合「Z」は部門(その他)を「8301」は分類番号を「2008」は発行年を示している。
部門記号の体系
部門記号は、産業分野ごとに体系的に割り当てられている。主要な部門記号とその対応分野は以下の通りである。
- A(土木及び建築)は建設分野全般
- B(一般機械)は機械要素や工作機械等
- C(電子機器及び電気機械)は電気・電子関連機器を対象としている。
- D(自動車)、E(鉄道)、F(船舶)、W(航空)は各種輸送機器を扱う。
- G(鉄鋼)とH(非鉄金属)は金属材料
- K(化学)は化学製品および化学分析を対象としている。
- L(繊維)、M(鉱山)、P(パルプ及び紙)、R(窯業)はそれぞれの産業分野の規格を扱う。
- Q(管理システム)は品質管理や環境管理などのマネジメントシステムを対象とする。
- S(日用品)とT(医療安全用具)は消費者に関連の深い製品を扱う。
- X(情報処理)は情報技術関連の規格
- Z(その他)は他の部門に分類されない規格を対象としている。
数字部分の構成
数字部分は階層的な分類体系を採用している。
最上位の1桁目は部門内での大分類を示し、2桁目は分野を表す中分類として機能する。
必要に応じて2桁目で更なる細分類を行うことも可能である。
規格番号の割り当ては分類ごとに通し番号方式を採用している。
2桁の場合は01から、細分類された1桁の場合は0から番号付けを開始する。
この方式により、規格の体系的な管理と将来の拡張性を確保している。
パート制の運用
複数の部分から構成される規格については、パート番号を用いて体系化されている。
例えば「JIS C 61326-1:2017」のように、ハイフンの後にパート番号が表示される。この方式により、関連する一連の規格を体系的に管理することが可能となっている。
採番における特別な配慮事項
規格番号の割り当てにおいては、既存の番号との重複を避けるため、必要に応じて番号を飛ばして採番することがある。
また、3桁以下の番号体系から4桁体系への移行過程で生じた飛び番号が存在する場合がある。
国際規格との整合性を図るため、対応する国際規格が存在する場合は、可能な限り国際規格の番号とJIS規格の番号を一致させる方針が採用されている。
これにより、国際規格とJIS規格の対応関係を明確にし、規格の利用者の利便性を向上させている。
改訂時の規格番号の取り扱い
規格の改訂が行われた場合、原則として規格番号は維持し、発行年のみを更新する方式を採用している。
ただし、規格の内容が大幅に改訂された場合や、規格の再構成が行われた場合には、新たな規格番号が割り当てられることがある。
このような柔軟な運用により、規格の継続性を保ちながら、技術の進歩や社会のニーズの変化に対応した規格体系の整備が可能となっている。
関連商品