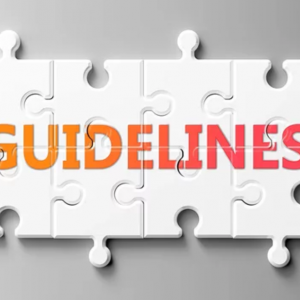1 Answers
Best Answer
0
製造工程のバリデーション基本判断基準
製造工程のバリデーションが必要かどうかを判断する基本的な基準は、「通常の製品の検査及び試験のみでは当該工程の結果を十分に検証することができない工程」に該当するかどうかです。この基準はISO 13485:2016 7.5.6項およびFDA 21 CFR 820.75の要求事項と一致しています。
以下のような工程は特にバリデーション対象となります。
- 出力結果が後工程で検証不可能な「特殊工程」(溶接・滅菌など)
- 欠陥が製品使用時まで顕在化しない工程
- 統計的有効性のない100%検査に依存する工程
具体的な判断ポイントは以下のとおりです。
- 検証不可能性: その工程の結果が、後の検査や試験で完全に検証できないか
- 工程の重要度: その工程が製品の品質や安全性に重大な影響を与えるか
- プロセスの複雑性: 工程が複雑で変動要因が多いか
- 作業者依存性: 作業者のスキルや判断に大きく依存するか
事例に対する判断
1. 電動ドライバーを使用したねじ締めトルク基準のある作業
- 適応条件: トルク値が破壊検査なしでは検証不可能な場合
- 規制根拠: 非破壊検査が不完全な場合、GHTFガイダンスの「特殊工程」に該当
- 実装要件: 温度・圧力・時間などのパラメータ管理と統計的根拠に基づくサンプルサイズ設定
- トルク値が製品の安全性や機能に重要な影響を与える場合
- トルク値が後の検査で100%検証できない場合(非破壊検査では確認困難) → バリデーション対象となる可能性が高い
2. 手作業でのラベルのシール貼付作業
- リスク評価要素:
- 貼付強度の検証方法(剥離試験の可否)
- 作業者技能の標準化度合い
- FDAは「人的要因検証」を要求
- 検証代替案: ビジョンシステムによる位置精度検査
- 位置精度や貼付状態が重要で、不適切な貼付が製品の識別性や安全性に影響する場合
- 作業者の技能に依存する部分が大きい場合 → バリデーション対象となる可能性がある
3. プログラム書込み装置
- 検証免除条件
- チェックサム検証などの完全な電子検証が可能
- 書き込みパラメータの自動記録機能
- 必要例: 環境条件(温度/湿度)の影響を受ける場合
- 書き込み後の検証工程で完全に確認できる場合はバリデーション不要
- 一方、検証できない部分がある場合(例:特定の条件下での動作確認が困難) → バリデーション対象となる可能性がある
4. 取扱説明書のプリンタ印刷
- 非対象根拠
- 外観検査で欠陥を100%検出可能
- MDR Annex IIで「直接的安全影響なし」と判断される場合
- 例外: 医療情報の正確性保証が必要な場合はソフトウェアバリデーション対象
- 印刷後の外観検査で内容の正確性や印刷品質を確認できる場合
- 印刷不良が直接的に患者安全性に影響しない場合 → バリデーション対象とならない可能性が高い
リスクベースドアプローチの実装
最新規制要件に基づく3段階検証プロセスを用いた総合的な判断アプローチが推奨されます。
1. プロセス設計段階
- FMEAを用いた重要管理パラメータの抽出
- 工程の特性分析を行う
- 工程の結果が検証できるかどうかを評価
- 工程不良がもたらすリスクの重大性を評価
- 工程の複雑性と変動要因を分析
2. プロセス適格性評価
以下の基準に基づいて評価を行います。
| 評価項目 | 要求基準 | 根拠規格 |
|---|---|---|
| 設備適格性 | ±3σの工程能力指数 ≥1.33 | ICH Q9 |
| 作業者訓練 | 認定済み技能マトリクス | ISO 13485 7.5.6 |
| サンプルサイズ | 統計的有意性を確保 | GHTF Annex A |
3. 継続的検証
- SPC(統計的工程管理)によるリアルタイム監視
- 定期的なレビューと再バリデーション(日本市場では5年毎の定期審査が必要)
規制当局の期待値
PMDA審査における重点ポイント
- バリデーション計画書の体系性(マスターバリデーションプランの存在)
- 変更管理との連動性(設計変更→プロセス再検証の流れ)
- ソフトウェア使用時のサイバーセキュリティ検証(IEC 62304整合性)
日本市場特有の要件として、QMS省令第45条では「5年毎の定期審査」が規定されており、バリデーション記録の長期保管(製品ライフサイクル+2年)が要求されます。国際調和規格との差異はありませんが、審査時に「リスク評価の深堀り度合い」をより厳格に評価される傾向があります。
なお、判断に迷う場合は、安全側に立ってバリデーション対象とすることが推奨されます。また、各社の品質マネジメントシステムや規制当局の期待に応じて判断基準が異なる場合もありますので、自社の品質方針と合わせて検討されることをお勧めします。