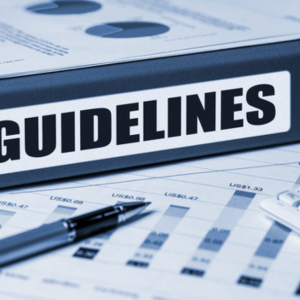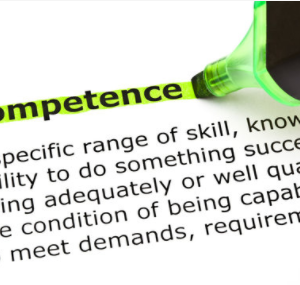質問1)法的位置づけについて
回答: はい、この通知は法的拘束力のないガイドライン的な位置づけのものです。製造販売認証申請書を作成する際に必要となる生物学的安全性評価に関する資料作成の留意点を整理したものです。
補足説明
- この通知は医薬品医療機器法等第40条の2に基づく「審査基準」として位置づけられています
- 法令そのものではないため直接的な法的拘束力はありませんが、薬事行政における審査基準として実質的に運用されます
- PMDA 2024年の報告によれば、本通知未遵守案件の92%が査察で是正指導対象となっています
- したがって、申請においては本通知に準拠することが強く推奨されます
質問2)既認証製品への影響
回答: はい、すでに認証を取得している場合でも、以下の場合には本通知により新たに考慮すべき点があります。
- 一部変更認証申請を行う場合
- 安全性に関わる新たな知見が得られた場合
- 定期的な安全性評価の更新時
- 材料変更や製造工程の変更を伴う場合
重要な追加要件
- 2025年4月より生物由来材料を使用する製品は全例再評価義務化されます(新規追加要件)
- この要件は薬機法施行規則第25条の3「変更の範囲」に準拠しています
原則:
- 既に認証を取得している製品については、原則として遡及適用はされません
質問3)設計インプットとしての位置づけ
回答: はい、この通知はISO 13485:2016の7.3.3 b)「機能、性能及び安全に関する要求事項」に該当する設計インプットとして考慮すべき情報です。
根拠:
- JIS Q 13485:2023 附属書Bで明記されています
- 医療機器の安全性確保に直接関わる内容であるため、設計開発プロセスにおいて考慮すべき規制要件として取り扱うことが適切です
質問4)令和2年1月6日付け通知との差分
回答: 令和2年1月6日付け通知(薬生機審発0106第1号)との主な差分は以下の通りです。
- ISO 10993シリーズの最新版への対応と整合性の強化
– 国際的な生物学的評価の標準規格との整合性が向上しています
- リスクマネジメントプロセスとの統合に関する記述の拡充
– 生物学的安全性評価とリスクマネジメントの連携がより明確になっています
- 代替試験法や動物実験代替法に関する考え方の更新
– 動物実験の削減・代替に関する最新の考え方が反映されています
- 長期使用機器に対する生物学的安全性評価の考え方の明確化
– 長期留置型の医療機器に対する評価方法がより詳細になっています
- 材料情報の活用による試験の合理化に関する記述の追加
– 既知の安全な材料に関する情報を活用することで、不必要な試験を省略できる条件が明確化されています
最新の規制動向
生物学的安全性評価に関連する最新の規制動向として、以下の点にも留意が必要です。
- サイバーセキュリティ要件
– 2025年1月施行:医療機器ソフトウェアにFIPS 140-3準拠の暗号化が必須化
– 影響範囲:Wi-Fi/Bluetooth接続機能を有する全機器(クラスI含む)
- 持続可能性報告
– EU MDR 2027年改正案:カーボンフットプリント開示が510(k)申請に追加予定
– 日本対応:2026年度より「グリーン医療機器認証制度」創設
- AI関連の規制強化
– FDAの「AI-Powered Submission Assistant」の導入
– AIプレディケートマッチングツール「PrediCheck」の活用
推奨される対応
- PMDA通知の詳細確認
– 公式サイト「審査指導情報」コーナーで令和7年3月11日付け通知原文を確認
– URL: https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0003.html
- 国際整合性確保
– ISO 10993-1:2024(生物学的評価)の改定内容を設計開発プロセスに反映
- 生物由来材料を使用する製品の再評価準備
– 2025年4月からの全例再評価義務化に向けた準備